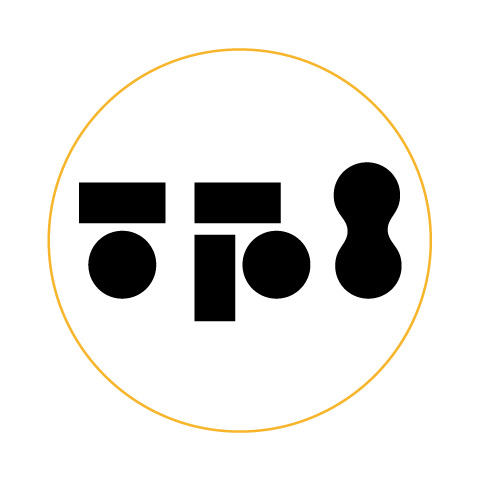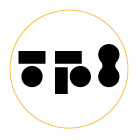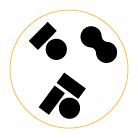【イベントレポート】リジェネレーションが拓く東京の未来:RegenerAction Japan 2024 開催(前編)
2024年11月25日、前年に引き続き、「RegenerAction Japan2024」が東京建物、Future Food Institute(FFI)、Tokyo Food Institute(TFI)の共催により、東京・京橋の東京コンベンションホールで開催された。
今年のテーマは「皆さんと一緒に、Regenerative City Tokyoを創る」。
リジェネレーションの認知拡大を目的とした前回から一歩踏み込み、世界の新たなロールモデルとなるRegenerative City Tokyoを実現するために、東京はどう進化するべきかを考えるトークセッション、アンカンファレンスセッション(ワークショップ)、展示・体験ゾーンを3会場で開催。オリジナルで開発した、リジェネラティブ・ランチボックスも本年から登場した。
関連省庁や企業、スタートアップ、アカデミアなど、さまざまな分野の識者が参加したイベントの模様を前編・後編にわたりレポートする。
オープニングには東京建物の代表取締役常務執行役員の古林慎二郎氏が登壇。
東京建物では現在、YNK-インク-(八重洲・日本橋・京橋)エリアで、リジェネレーションの思想を取り入れた街づくりに取り組んでいる。2024年12月2日に東京建物本社がある東京建物八重洲ビルの地下2階に食の教育施設「Gastronomy Innovation Campus Tokyo」※とリジェネラティブをコンセプトに据えたイノベーティブキッチン「8go」を併設したTokyo Living Labを開設した。
※Gastronomy Innovation Campus Tokyoについてはこちら

「昨年までは世界の潮流としてリジェネレーションが広まりつつあると言われても、日本では全く実感がありませんでした。そこから1年が経過し、日本でも色々なところでリジェネレーションという言葉を耳にすることになり、劇的な変化を感じています。人々と社会、環境が本当の意味で豊かになるにはどうしていくべきか。このカンファレンスを通じて、広い視野で気付きを得て、今後の活動に繋げていただければうれしく思います」と開催の趣旨と意義を語った。
世界のリジェネレーションの最前線
カンファレンス会場では基調講演とクロストークが開催された。
最初に登壇したのは、経済産業省資源エネルギー庁制作課長の村上貴将氏。現在世界中でCO2削減が求められているが、日本は世界5位の排出量となっており、その大部分がエネルギー起源となるため、エネルギー政策は重要な取り組みとなっている。
「日本は2050年のカーボンニュートラル達成に向けて、さまざまな取り組みを行なっています。2023年にはエネルギー政策と産業政策を一体化して行うGX推進法などを制定。また日本は世界に先駆けて、2017年に水素戦略を策定し、水素の導入量を引き上げるとともに、国内産水素のサポートや、既存エネルギーとの価格差支援などを進めています。また、現在日本は洋上風力発電がほとんど導入されていませんが、周囲を海に囲まれた国土だからこそ、ポテンシャルは高いと思っています」と日本のエネルギー政策の現状を解説。

イタリア南部、ポリカに拠点を構え、イベントの共催も務めるFFIは、行政や企業、アカデミアと連携し、世界各地でエコシステムを構築している。今回は創設者のSara Roversi氏が登壇し、「Regenerationに向けた新たなリーダーシップ」について語った。
「私たちは2018年に気候変動に関する動画を制作しました。ところが5年以上経った現在でも、状況は改善するどころか、私たちの想像の域を超える壊滅的な事態となっています。スペインのバレンシアでは1年に5回も大洪水が起こりました。これは過去100年を見ても類がありません。世界各地でこのような自然災害が起こり、警鐘を鳴らすレベルの危機に陥っている。私たちが直面する課題はとても大きいため、協調して真の変化を起こすためのアクションが必要です。そのために私たちのエコシステムの裏側では、教育、コミュニティ形成、イノベーションを3つの柱として活動しています」と語り、環境問題に関わるデータなどを提示しながら、FFIが世界各地で行っている事例を紹介した。

続いて、サステナビリティに関する世界最大級のデータベースを構築するHowGood社のEthan Soloviev 氏がオンラインで参加し、「再生型食品システムを中心とした進化論的対話」について講演。
「システム全体でリジェネレーションを考えるレベルになると、テコ入れできるポイントを考える必要があります。これは鍼のようなものです。正しい位置に鍼を打つと、全身が改善されるように、正しいところを押せば、全体の流れが大きく変わることになる。HowGoodでは600以上のデータソース、35万個の個別のデータ、製品に対する390万の評価データを蓄積しています。これらを世界の原料メーカーや食品企業などが活用し、改善方法を見極めています。ただし、これだけでは強力なツールではありません。さらに上位でリジェネラティブなフードシステム全体に取り組んでいるのが『Regen House』です。これはCOPや世界経済フォーラムなどに合わせ、世界中でイベントを開催し、政府関係者や金融関係者が食べ物を囲みながら包括的な議論をすることで、物事を加速度的に進めることを目的としています。大規模ではありませんが、グローバルな金融や食品企業の役員等や政府関係者が直接対話することでシステムの変革を考える試みになっています」
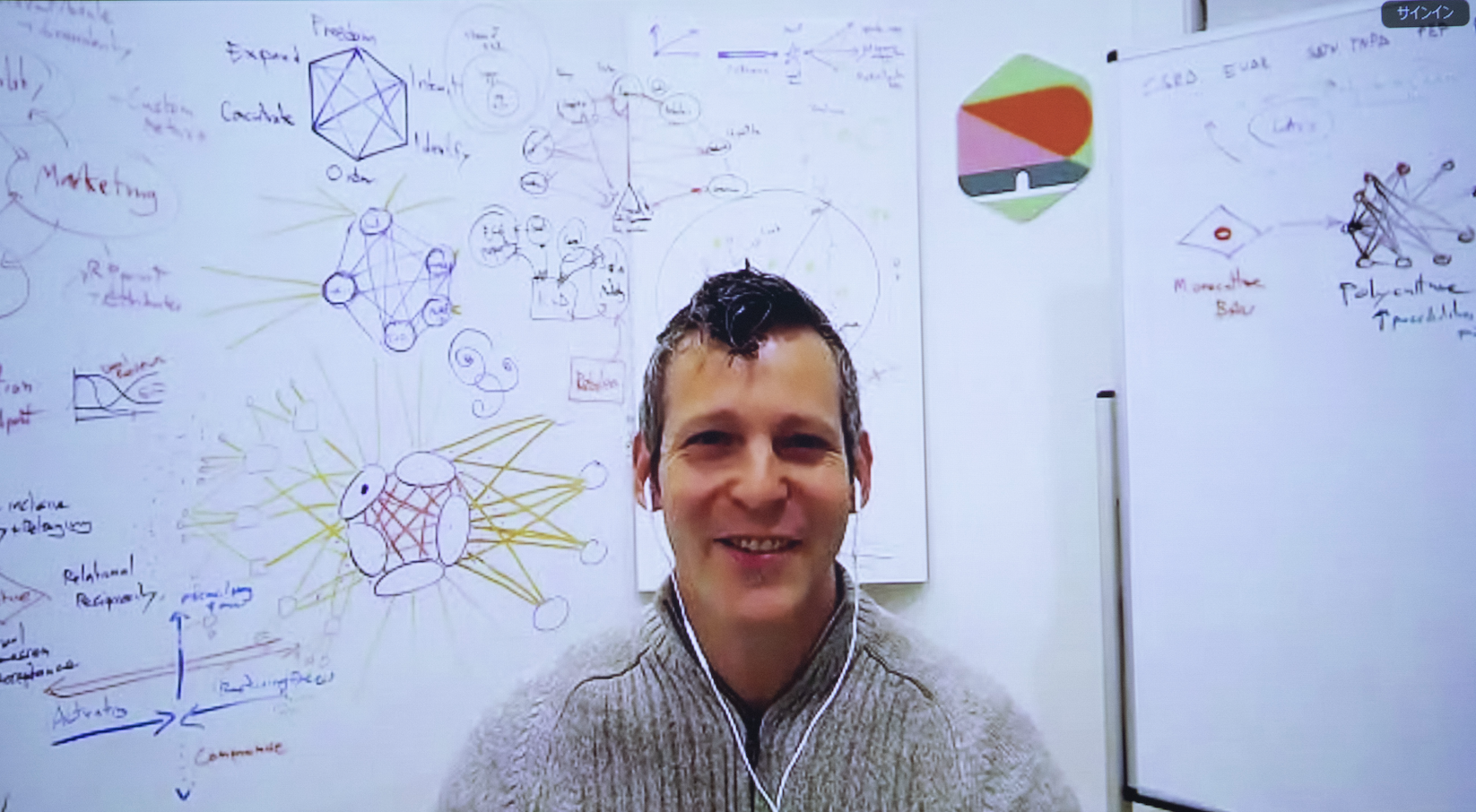
国際的な経営コンサルティングファームNOW PartnersのMerijn Dols氏のテーマは「パラダイムシフトの促進」と「再生型の未来に向けた経済と生態系の再構築」をテーマに、効率性を中心とした世界観から、効果を中心とした世界観へのパラダイムシフトの必要性を説いた。
「例えば『ナチュラ』という企業は、世界第5位の美容関連企業グループでありながら、220万haの雨林を保全し、栽培した種子などで製品を作り、世界で600万人の女性を雇用し、女性の権利活動も行なっています。ではナチュラは、企業なのか、保全機関なのか、女性の権利団体なのか。全体と各組織、そして連携している地域社会や生態系に対して一番ベストな結果は何かという、これまでと違うレンズを通してビジネスを設計すれば、利益を得ながら、世界に良い影響を及ぼすビジネスが可能になります」と、リジェネラティブに取り組むさまざまな企業の実例を挙げた。

AI時代の人間のあり方を考えるクロストーク
続いて、筑波大学の落合陽一氏と、「PLANETS」編集長の宇野常寛氏が「デジタルネイチャーの時代に人々はどのように生きるべきか」を議論。
落合氏が提唱するデジタルネイチャーとは「人・モノ・自然・計算機・データが接続され、脱構造化された新しい自然」を定義したもの。AIで拡張された世界で、人間の生き方はどう変わるのかが議論されるなかで、会場の話題となったのが「豊かな衰退」というキーワードだ。
「日本は人口が減り、緩やかに衰退し、緩やかに後進国化していくと考えています。ただし一人当たりの資源分配量は比較的高くなるので、豊かになる。つまり豊かな衰退です。これはリジェネレーションそのものでしょう。つまり我々の国はリジェネレーション先進国=豊かな衰退国になるということです。一般的な衰退は人口が減ってインフラが壊れたりしますが、これからロボットがインフラを維持し、少なくなった人間の知的産業をAIが維持するため、貧しくなることはない」と語る落合氏は、デジタルネイチャー時代における人間の生き方として、狩猟採集的な知的生産や創造活動を「マタギドライブ」と提唱もしている。
「マタギドライブのような人間が意識的にクリエイションするのではなく、AIから獲得するという制作のアップデートにより、人間の精神生活は大きく変わる可能性がある」と宇野氏が語るなど、人間性のリジェネレーションの課題についても語られた。

早稲田大学大学院の入山章栄氏と高倉&Company共同代表の髙倉千春氏は「Regenerationと経営戦略」をテーマに、AIが加速する現代において人の持つ役割は「答えがないなかで決めること」(入山)に変わると推察。その中で特に二人が着目しているのが地方と多拠点生活だ。
「今、東京から人材が流入している地方の市役所が面白くて、日本のリジェネレーションは確実に地方から来ると思っています。東京は課題が少ないが、地方は人手が足りず、自然が多くて、課題もたくさんある。東京だけに定住している人はオワコンになり、東京と地方や海外を移住しながら生活するようになっていくことが大切」(入山)。
「AIが進んだこれからの経営には、五感のセンスが勝負になるでしょう。そのためにも地方や海外で、それまでと違う環境に身を置いて、五感を養うことはこれからの時代、非常に重要です。実際、シリコンバレーのテック企業の採用条件を見ると、宗教や哲学、倫理など、抽象的な領域の研究をしている人を求めています」(高倉)と、これからの時代の人材育成や経営のあり方について語った。

午前の部の最後には、FFIの深田昌則氏とUnlocx代表取締役CEO田中宏隆氏が登壇し、午前中のセッションを総括。
「世界では、お金を稼ぐほど世の中が豊かで幸せになり、自然資源も無尽蔵にあるという前提の搾取的な社会は限界だという流れになってきていることを実感しました。お金や時価総額という一元的な価値を最大化するのではなく、多元的な価値が求められている。その多元的価値のヒントが前半のセッションには、多く散りばめられていたと思います」(田中)
「Merijn氏が『効率的な経営よりも効果的な経営』と話していましたが、イノベーションは様々な偶然やアイデアのぶつかりによって生まれてきました。だからこそ人との出会いやネットワークなど、人間の役割がますます重要になってくるでしょう」(深田)
.png)
東京建物のリジェネレーションへの取り組みとは?午後のクロストークへ(後編へ続く)
<文 / 林田順子>