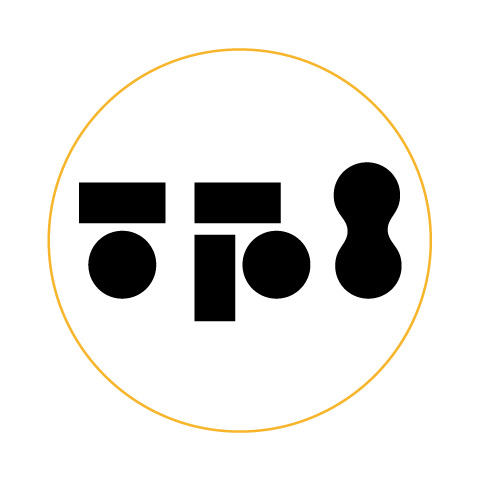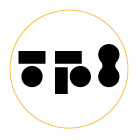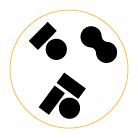【イベントレポート】【石川伸一氏】科学者・シェフ・参加者が共創する「サイエンストークカフェ」(後編)
「Gastronomy Innovation Campus Tokyo」(GIC Tokyo)にて、サイエンスアドバイザーを務める宮城大学食産業学群教授の石川伸一氏(当社団理事)と、ガストロノミーアドバイザーを務める野田達也シェフにより行われた、サイエンストークカフェ。科学者とシェフの協働によるセミナーの模様を前編に引き続きお伝えする。
あえて“おいしい”で終わらせない食のサイエンス
2025年1月に行われた第2回サイエンストークカフェのテーマは「凍結粉砕」。
これまで食品に「熱を与えること」が調理の中心だったが、近年、液体窒素のよって「熱を奪う」ことが、新しい調理方法として使われるようになってきている。
「-196℃の液体窒素は食品を瞬時に凍らせることができ、さらに粉砕することで、野菜の皮や果物の種も可食化できます。そのため、最近では食品ロス削減の手段のひとつとして注目を集めていて、さまざまな活用法が考えられます。たとえば、液体窒素を用いた凍結粉砕は低温での加工が可能なため、香気成分や熱に弱いビタミンなどの栄養素が損なわれにくく、素材の持つ風味や栄養価を高いレベルで保持できます。これにより、これまでの加熱加工では実現できなかった香り高い粉末スパイスや、色鮮やかな野菜パウダーの製造も可能になります。今後、液体窒素技術は、ガストロノミーから食産業全体にまで広がる可能性を秘めています」
本セッションでは、試食を行う体験型講義によって、調理における液体窒素利用の可能性について考えるものとなった。
「講義部分では、切ることと加熱調理をすることが、二大調理操作であること、また加熱調理がヒトの進化に大きな役割を果たしてきたことを解説しました。一方で加熱調理の真逆にあるとも言える冷却調理法は、近年「冷凍ブライパン」や『ロースアイス』の登場などを例に挙げて、一つの調理操作となっていることを説明しました」
試食では、いちご、みかん、バナナなどの果物、トマト、大根、長ネギ、生姜、わさびといった野菜や薬味を凍結粉砕し、試食を行なった。
「この回では、ある程度食材を色々用意しておいて、参加者の方に何を凍結粉砕したいか意見を伺って、調理をしました。実は、私は最初からちょっとおいしくないものを食べさせたいと思っていたんです。というのも、おいしいものは『おいしいね』で終わってしまうのですが、まずいと色々と理由を考えてくれるんです。活発な議論を促すため、あえておいしいものを食べさせすぎないようにというのは狙っていました」
今回、「みなさん露骨に無言になりました」と不評だったのはバナナの皮。一方で大根は凍結した輪切りのものと、粉末状にしたものを食べ比べてもらっている。
「食材の香りが立ったり、甘味が抑えられたり、苦味が増したり、食材それぞれの特徴を感じられたようです。また野田シェフは、ゆずの砂じょう(柑橘類の果肉部分に含まれる粒)を液体窒素でバラバラにし、それに凍結粉砕したゆずの皮をまぶしたものを提供していただきました。この技は、香りの揮発特性や時間による味覚変化を計算した構成になっています。皮の精油成分が口に入れた瞬間に立ち上がり、低温によって甘味が引き締まり、ゆず特有のほろ苦さが後味として残るものでした。私自身、凍結粉砕の技術は研究の中で扱ってきましたが、それを「完成された料理」として提示する発想は持っていませんでした。科学者が提供できるのは、食材の分子構造や成分の変化を最大限に引き出すための理論や技術です。一方、料理人はそれを人が食べる喜びにまで落とし込む感性と構成力を持っています。今回のその一皿は、その両者がかみ合った瞬間の好例であり、参加者にも一番好評でした。今後、こうした融合は、単なる調理技術の紹介にとどまらず、五感を設計する新たなガストロノミー表現へと発展する可能性を強く感じさせるものでした」
三者三様の意見が新たな食の可能性を導く
2025年3月に開催された第3回は、「圧力鍋の逆の調理法〜減圧による含浸・抽出調理の可能性」をテーマに行われた。

圧力鍋は、圧力が高くなるにつれて上昇する水の沸点を利用し、高温の水で食材に熱を伝えることで、食材を柔らかくする。一方で、減圧調理は、鍋の中の気圧を下げて、真空に近い状態にすることで、温度を正確にコントロールし、素早く味を浸透させて、調理時間を短くし、柔らかい食材でも潰さずに調理することが可能だ。
「講義では、この圧力と調理に関する基本的な解説を行いました。減圧調理は、容器の中の空気を抜いて気圧を下げ、食材の中の空気やガスを外に出します。すると食材の中に小さなすき間ができ、気圧を戻すときに、そのすき間に調味液や香りが一気に入り込みます。この仕組みにより、普通よりも短時間で味を中までしみ込ませることができます。また、減圧すると沸点が下がるため、低い温度でも香りやうま味を効率よく取り出せます。実際、減圧調理器『Vide Pro』を使い、さまざまな抽出・浸透実験を行いました。時短で抽出・浸透が可能な昆布出汁、染みこみにくいりんごとコーヒーやグレープフルーツジュース、大根とオリーブオイルなどで実験を行い、減圧調理以外の調理法との食べ比べなども行いました」

参加者は、例えば普通にコーヒーにつけたりんごは苦味を強く感じる一方、減圧調理ではりんごの甘さとコーヒーの風味に一体感を感じられる、減圧で調理された大根は甘味をより強く感じる、減圧により透明感のある見た目になったなど、味わいだけでなく、見た目の美しさにも言及し、減圧調理の可能性を体感した。

「3回のセッションを通して、テーマと人の掛け算で、色々なサイエンストークカフェが展開できると感じました。特にスタートアップの中には、新しい食材を作っても、それをどうやって料理にするかというアプリケーションがないと、市場は発展しないものも多い。そこで、シェフの創造力によってその食材が一皿の料理に姿を変え、科学者の分析や検証によってその魅力や機能性が裏付けられ、さらに参加者のからの多様なフィードバックが加わることで、いろいろな可能性が広がると感じました。また講義と調理実演を並行して行える設備が整っているのがGIC Tokyoの利点です。これにより、参加者は知識と体験を結びつけた理解ができ、アイデアがその場で膨らみます。今後はリアルな場だけでなく、オンラインで国や言語を超えたセッションを行うことで、日本のコンテンツを世界に広げられると思っています」
GIC Tokyoでは今後も食の新たな可能性を創出するプログラムを提供していく予定である。その取り組みに注目をしていきたい。
▼前編はこちら
【イベントレポート】【石川伸一氏】科学者・シェフ・参加者が共創する「サイエンストークカフェ」(前編)
石川 伸一
Shinichi Ishikawa

東北大学大学院農学研究科修了。北里大学獣医学部専任講師、カナダゲルフ大学食品科学部客員研究員、宮城大学食産業学部准教授を経て、現在、同大学食産業学群教授。分子調理研究会代表。著書に『クック・トゥ・ザ・フューチャー』『分子調理の日本食』『料理と科学のおいしい出会い』『かがくを料理する』『「食べること」の進化史』など多数。
Gastronomy Innovation Campus Tokyo(GIC Tokyo)
東京都中央区八重洲1丁目4-16
八重仲ダイニング 地下2階
https://gictokyo.com/
https://tokyofoodinstitute.jp/column/gict-open/
<文 / 林田順子>