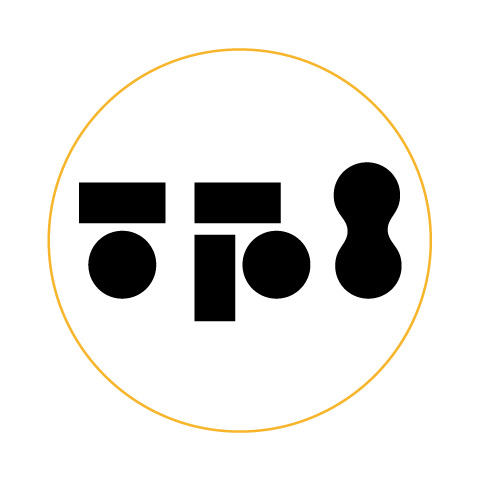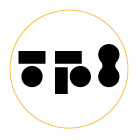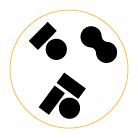【イベントレポート】【石川伸一氏】科学者・シェフ・参加者が共創する「サイエンストークカフェ」(前編)
世界中のシェフや起業家、科学者、イノベーターを結びつける食のエコシステムのハブとして創設された「Gastronomy Innovation Campus Tokyo」(GIC Tokyo)では、食分野における人材育成、地域文化の振興、日本の食文化のグローバルな普及を目的とした多彩な教育プログラムを提供している。
今回は、TFIの理事であり、同施設のサイエンスアドバイザーを務める宮城大学食産業学群教授の石川伸一氏と、ガストロノミーアドバイザーを務める野田達也シェフの協働により、2024年12月19日から3回にわたり行われた、「サイエンストークカフェ」の模様をレポートする。
科学者とシェフの知見が融合したサイエンストークカフェ
サイエンストークカフェは、この設備をフル活用し、学術的アプローチを石川氏が、実践的なアプローチを野田達也シェフが担い、理論と実践が融合したセミナーとなった。また、参加者は常時、チャット機能で感想や質問を送ることができ、聴講するだけなく、三者が双方向的にコミュニケーションを取れるようにした。

「このコラボレートは私にとっても大きな学びとなりました。私は料理を科学的に分析し理論を構築する立場であり、野田シェフは現場で味と体験を創り出すスペシャリストです。さらに参加者は食への感度が高い人たちでした。科学者は技術的な説明や数値的な分析で止まってしまい、そこからガストロノミーへと進化させるには、やはり料理人のプロフェッショナルな感覚と創造性が必要なわけです。また、参加者の中には調理師学校の教員の方などスペシャリストもいらっしゃったので、多様な視点で、面白い意見をたくさんいただいて、そこからさらに議論が生まれる。こうした双方向のやり取りは、単なる足し算ではなく、かったく新しい発見を生む掛け算の関係で、想像以上にとても盛り上がりました」と石川氏は語る。

参加者との試食を通じ、炭酸食品の可能性を探る。
2024年12月に行われた初回のサイエンストークカフェのテーマに選ばれたのは『炭酸食品』。
「清涼飲料水の中で、炭酸飲料の生産量が最も多く、その生産量も年々増加しています。実は炭酸飲料には単なる爽快感を与えるだけでなく、炭酸がのどを刺激することで、飲み込む運動が促進され、高齢者の嚥下機能を改善する可能性があると考えられていて、実際に飲み込む機能を改善する研究も報告されています。これらの機能はリハビリや介護食分野での応用が期待されています。しかし、『炭酸食品』はパチパチするキャンディぐらいで、市場にはほぼ存在していません。そこで、今回のセッションでは、炭酸を固形物に封じ込めるという新しい食品の可能性に着目しました」
セッションでは、ガストロノミーで活用されるエスプーマボトルを活用。これは食材に亜酸化窒素や二酸化炭素を加えることで、食材を泡状にする機材で、固体食品の炭酸化を行うこともできる。実際にセッションで調理をし、試食して、ディスカッションを行った。

野田シェフは、いちごやシャインマスカットなどの果物、大根、にんじん、きゅうりなどの野菜スティック、木綿豆腐、厚焼き卵、梅がゆなど、さまざまな食材をエスプーマボトルに入れ、炭酸ガスを注入。2時間ほど冷蔵庫で放置後、ガスを解放し、参加者と試食をし、その特性を評価した。
「固形の炭酸食品という未体験の食感は、多くの参加者にとって衝撃的な体験となったようです。好評だったのは果物類。果物と炭酸はもともと相性が良く、特にシャインマスカットは、炭酸を含んで皮がパンパンに張った見た目や、シュワシュワとした音も含めて、五感で楽しめる食品となりました。この食品の炭酸化技術は、高齢者の嚥下機能サポート食品としてだけでなく、スイーツや前菜、さらには演出効果を重視するガストロノミーの世界でも活用可能です。嗜好性と機能性を兼ね備えた新しい炭酸食品は、飲料と食品の境界を越えた新ジャンルを切り開く可能性を秘めています」
同じ果物でも、いちごは従来の食感や形が失われる、酸味を強く感じるなど、ネガティブな意見が多く、炭酸化の向き不向きが顕著になった。一方で炭酸食品の可能性を感じさせる感想も多く寄せられた。
「野菜スティックは漬物のような味がする、豆腐は大豆臭を感じなくなったなど、さまざまな意見が出ました」

また、炭酸化した麻婆豆腐や、卵焼きは冷やし中華と一緒に使ったら、楽しい体験になりそうなど、積極的なアイデアも出され、新しいメニューの種が生まれることを強く感じた回となったという。
「また、野田シェフからも、調理現場の経験に基づいた専門的な提案や改善点をいただくことができました。それは、私が実験室で培ってきた知見とはまったく異なる視点であり、互いの専門性が触発し合う瞬間でした。日本において「料理人と科学者の融合」が形となった現場であり、GIC Tokyoから生まれた議論や試作は、これまでの延長線上にはない新しいガストロノミーの可能性を感じさせてくれるものでした」
▼後編はこちら
【イベントレポート】【石川伸一氏】科学者・シェフ・参加者が共創する「サイエンストークカフェ」(後編)
石川 伸一
Shinichi Ishikawa

東北大学大学院農学研究科修了。北里大学獣医学部専任講師、カナダゲルフ大学食品科学部客員研究員、宮城大学食産業学部准教授を経て、現在、同大学食産業学群教授。分子調理研究会代表。著書に『クック・トゥ・ザ・フューチャー』『分子調理の日本食』『料理と科学のおいしい出会い』『かがくを料理する』『「食べること」の進化史』など多数。
Gastronomy Innovation Campus Tokyo(GIC Tokyo)
東京都中央区八重洲1丁目4-16
八重仲ダイニング 地下2階
https://gictokyo.com/
https://tokyofoodinstitute.jp/column/gict-open/
<文 / 林田順子>