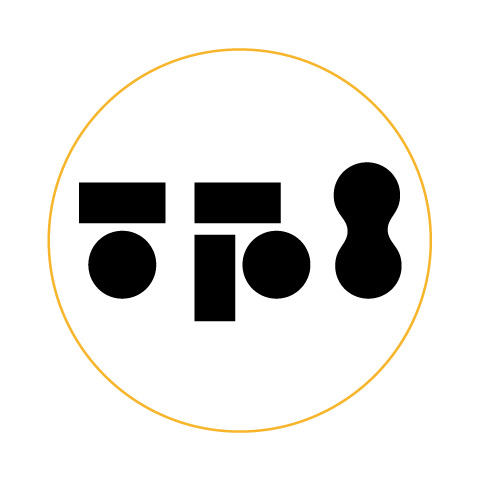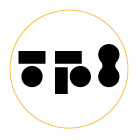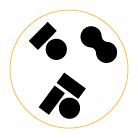【イベントレポート】「リジェネレーション」がテーマの国際カンファレンス「RegenerAction Japan 2024」(後編)
2024年11月25日、Regenerative City Tokyoを考える「RegenerAction Japan2024」が東京・京橋にある東京コンベンションホールで開催された。このイベントの模様を前編に続き、お伝えする。
健康、デザイン、自然の視点で語るリジェネレーション
午後の部は東京建物の代表取締役専務執行役員 和泉晃氏と、日経BP日経ESG編集長の馬場未希氏が登壇し、東京建物のリジェネレーションへの取り組みについて語るところからスタートした。
東京建物が手がけた「大手町タワーの森」は開業から10年を経て、レッドリストに記載される植物や鳥類などが観測されるなど、都心が失いつつある豊かな自然環境の再生に成果が出始めている。また都立明治公園でのPark-PFI事業では「最初の20年ぐらいは人間の手を入れて森を育成し、その後は自然と森になる、100年続く森づくりを目指しています」(和泉)など、東京建物が手がけるリジェネラティブな街づくりの実例が挙げられた。
「単に森や場を作るだけでなく、そこから自然が増えたり、人が新しいものを得る姿はまさにリジェネラティブのコンセプトに繋がると感じました」(馬場)

続いてのクロストークのテーマは「Longevity(ロンジェビティ)の最前線」。グローカリンク取締役の西川信太郎氏、慶應義塾大学特任講師の早野元詞氏、Rhelixa代表取締役CEOの仲木竜氏が登壇。日本では健康長寿と訳されることが多い「ロンジェビティ」。ここでは主に世界と日本との健康長寿に関する意識や取り組みの差について語られた。
「デビッド・シンクレア著の『LIFESPAN』という本の中では、老化が病気であると書かれています。2015年頃から研究レベルでは健康寿命を延伸する技術や、最大寿命を30~40%伸ばす技術がすでにできています。エイジングは評価できて、細分化できて、治療できる世界になってきている。アメリカでは不老の社会になったときに、どういう社会を作るのかという話にまで発展しています」(早野)、「日本は抗加齢への注目度が高いが、アメリカを中心とした海外は、老化をいかに防ぐかに興味があって、資産家が巨額の投資も行っています」(仲木)、「僕はロンジェビティに関する2つの産業を注目しています。1つは若返られせる技術、1つは老化を測定する技術。特に老化測定が進めば、実年齢ではなく、身体的年齢で雇用される世界になるでしょう」(西川)
長寿国である日本はロンジェビティへの優位性が高い。企業間で連携して、領域としてのコンソーシアムを作ることが、日本がロンジェビティ先進国になるカギだと語った。

続いて日経BP総合研究所の安達功氏がファシリテーターとなり、サステナブルビルディングコンサルタントの蒔田智則氏、Takramデザインエンジニアの緒方壽人氏、ソニーグループのサステナブルデザイングループ総括部長である西原幸子氏が「レジリエントな街づくりとインクルーシブデザイン」について語った。
デンマークでリジェネラティブな建築やデザインなどを手がける蒔田氏は「気候変動だけでなく、環境破壊など、もうタイムリミットはないと考えていいでしょう。その中で昨日と同じことをやるのでは、うまくいかない。色々な人と話をして新しいアイデアを組み込むことで、人間だけでなく、植物、動物、全てを巻き込んだ街づくりをしないと本当に危険なことになる」と実例を挙げながら語った。
「AIは人間の敵かに味方か、二分法的に語られがちですが、どんな道具やテクノロジーにも人間の能力を高める最初の分水嶺と、行き過ぎて逆に人間の力を奪ってしまう分水嶺がある。つまり不足と過剰のラインがあり、その間には幅があるので、その幅の中でいかにバランスを取ってデザインをするべきかが問われる。実はそのためのテクノロジーはすでに存在していて、それをリジェネラティブな方向にどう組み合わせるのかが大事な部分になってくる」(緒方)
「サステナビリティというと消極的になり、作らない、消費しないという方向性になりがちだったが、リジェネラティブは作り、生み出していくことがプラスの価値になるというポジティブなメッセージと捉えてほしい」(西原)

「文化遺産の進化と未来への継承」についてのクロストークではTFI代表理事の沢俊和がファシリテーターとなり、造園ユニット「veig」の片野晃輔氏と西尾耀輔氏、盆栽を取り扱う松葉屋代表取締役社長の小島哲平氏が登壇。自然と共生し、生活を豊かにしてきた日本人ならでは自然との向き合い方について語り合った3人が共通して口にしたのは「自然は人間の寿命と重ね合わせたときに交わりきれない部分がどうしても出てくる」ということだ。
「盆栽は何百年も生きます。となると僕一代で築けるものではなく、過去に盆栽を世話し、愛でた人がいて、僕が同じように育て、そして次の世代に受け継いでいく。僕の盆栽というよりは、託されたもの、引き継いでいるものという考えで盆栽を愛でています」(小島)、「自然保護では植林にフォーカスされることが多いが、私たちが手がけた個人宅のベランダでは30種類120本を過密に混植することで、競争させて、成長をあえて遅くしました。メンテナンスの手間を省き、自然の摂理で管理ができるようになっているのです」(西野)、「エコロジーの話をすると縛り付けるような話が増えるが、そうなると持続性がなくなっていく。例えばアフリカのプロジェクトで、アメリカの富豪が植林をしても大体が失敗する。それは現地の人が好きになれないからです。自然環境には文化的なものが多分にあるので、人間が感動できる空間がないと持続性が損なわれると考えています」(片野)
話を聞いた沢氏は「サステナブルなどの概念よりも、好きになること、感じることの重要性を感じました。リジェネレーションを難しく考えるのではなく、東京で散歩をしながら、木や雑草に目を向けて、心を寄せることが、豊かな社会を作るヒントになるのではないか」と総括した。

リジェネラティブな食材を使ったランチタイム
昼食時には「食を通して、リジェネレーションを体感する」をテーマにした、山と海、2種類の「リジェネレーション弁当」が参加者たちに振る舞われた。
「山のリジェネレーション弁当」は株式会社シェアダインが監修を行い、青森県十和田市のオーガニックファームNATUROBEと日本草木研究所の食材を使用。牛や野菜、蜂などの連携を図ったリジェネラティブアグリカルチャーで生産された特別栽培米や、天然きのこのバターソテーなどのメニューが並んだ。
「海のリジェネレーション弁当」には合同会社シーベジタブルが提供する海藻をふんだんに使用。世界では海藻がトレンドになっているが、50種類以上の海藻を食べる食文化を持つ日本はその先進国でもある。
シーベジタブル共同代表の友廣裕一氏は「その海藻が現在の日本では壊滅の危機にあります。私たちは海上と陸上で栽培する技術を持ち、料理開発も行っています。今日は普段食べたことのない海藻も入っていると思うので楽しんでほしい」と語った。

社会課題の解決視点を養うワークショップ
午前中には、中ホールにてRidilover(リディラバ)によるワークショップが実施された。
社会課題を構造的に捉える手法を学び、食品ロスをテーマに、自身の事業領域や立場から課題解決の糸口を探る実践的なプログラムが展開された。
ワークショップは食や流通、デベロッパーなどの企業、スタートアップ、アカデミアなどが参加し、3グループに分かれて3スロットで実施。普段は意識しにくいバリューチェーン上の中間プレーヤーの存在や影響に気づきが生まれたほか、参加者それぞれの業種やバックグラウンドによって着目する領域が大きく異なることも共有された。
「社会課題という大きな言葉だと大変そうに思えるが構造化して細分化することで、さまざまな可能性が生まれることが分かった」、「気付き与える仕掛けとしては有効だし、実践しやすいフレームワークだった」など、参加者からは実用性と学びの深さを評価する声が多く寄せられた。

異業種の共創でRegenerative City Tokyoについて考えるアンカンファレンス
同じく中ホールにて開催された「Regenerative City Tokyo」を実現するために、我々は何をすべきかなどを議論するアンカンファレンスには、食や流通、デベロッパーなどの企業、スタートアップ、アカデミアなどが参加。6つのグループに分かれて、それぞれが東京の抱える課題、街の魅力、そしてリジェネラティブな未来へのアクションについて話し合い、プレゼンテーションが行われた。
カルチャーを軸に捉えたグループからは、色々な文化が雑多に混ざり合う東京の魅力を、ミュージアムや多彩な文化が集まる「文化横丁」として発信するアイデアが創出された。
ヒューマンをテーマにしたグループは、手段としての東京での働き方は、テイクばかりでギブをしないと問題を提起。関係性を修復するイベントや、コミュニティを強化するデザインプロジェクト、デジタル技術を活用したお節介のタギングなどのアクションが提案された。
東京を消費の街と位置付けた2つのグループは、それぞれ経済と、地球という違うアプローチから未来図を描いた。ゴミとなるものにストーリー性を付与して還元したり、一次産業に大手企業が連携して高付加価値をつけるなど、様々な視点でのアイデアが生まれた。
また社会関係資本が貧しいオフィスエリアでの文化の継承もアイデアとして挙がった。都市の人口密度の高さを逆手に取り、愛着の醸成や人々のアイデンティティ確立のための様々なアクションが提案された。

リジェネレーションの実装に触れる展示・体験
会場にはリジェネレーションを実装した事例の紹介や商品を体験できる展示も行われた。
ランチの食材を提供したNATUROBE、日本草木研究所、シーベジタブルに加え、クロストークに登壇したveigの取り組みや松葉屋の「TRADMAN’S BONSAI」の盆栽も展示。
他にも使用済みパラグライダーやペットボトルリサイクル生地を使用したバッグを展示したHOZUBAG、リサイクル可能なアルミを使った水を配布したジャスティス、また役割を終えたウィスキー樽を使った「サントリー樽物語シリーズ」の家具を展示したサントリーのブースも話題となった。


日本の伝統文化であるお茶を世界に発信するTeaRoomと、金沢に拠点を持つクリエイター集団seccaが、東京建物と取り組んでいる、オフィスワーカーのウェルビーイング向上支援サービス「オフィスで茶の間」体験は、高品質なお茶が手軽に楽しめると参加者の関心を集めていた。

9時間にわたり開催された「RegenerAction Japan2024」のクロージングでは、FFIの深田昌則氏とTFI代表理事の沢俊和が登壇し、異業種での共創を改めて呼びかけるとともに、今年のカンファレンスから得たアイデアをこの先1年で具体のアクションに移し、来年のこの場で報告したいと語った。これからの1年、参加者それぞれがどんなアクションを起こし、2025年のRegenerAction Japanでは何が語られるのか。ここから始まるRegenerative City Tokyoに注目したい。

<文 / 林田順子>